海と富士の茶の間で味わう富士山麓に息づく富士御茶【静岡県・富士市】

全国有数の茶処、静岡県には「茶の間」と呼ばれる、茶畑に囲まれたテラスを貸し出すサービスがあります。現在、静岡には6つの「茶の間」があり、今回はその一つである「海と富士の茶の間」を訪れました。ここでは、富士山、愛鷹山、駿河湾を一望しながら、お茶を楽しむことができます。
迎えてくれたのは、「海と富士の茶の間」のオーナーである「富士山まる茂茶園」の代表取締役、五代目の本多茂兵衛さんです。
この記事では、「海と富士の茶の間」の魅力と、静岡県100銘茶協議会の会長も務める五代目・本多茂兵衛さんのお茶作りに対する哲学を、全編インタビュー形式でお届けします。
目次
「海と富士の茶の間」とは
北に「富士山」と「愛鷹山」を背に、南には「駿河湾」を見下ろし、心地よい風が吹き抜ける小高い丘に広がる茶畑。この絶景の地に「海と富士の茶の間」はあります。


「海と富士の茶の間」のオーナーであり、「富士山まる茂茶園」の代表取締役である五代目本多茂兵衛さんにお話を伺いました。

–ここが「海と富士の茶の間」ですか。とても爽快な場所ですね。静岡に住んでいる私も、こんな場所があるとは知りませんでした。
実はこの「海と富士の茶の間」は「海と富士山の見える茶園」の名前でグーグルに「美術館」として登録されているんですよ。
これまでお茶摘み体験の会場として使用していたのですが、ここでお茶が飲めるようになったらもっと素敵だなと思いまして。植物・植生をテーマに活動している現代アーティストの山本修路くんと一緒に「あずま屋」を作っちゃいました(笑)。
使用している木材は、平成30年の夏に富士山から切り出した「富士ひのき」。名付けて「海と富士の茶の間」です。

「海と富士の茶の間」は、どなたでも自由に貸し切りでご利用いただけるように、自社サイトや専用の予約サイトからご予約いただけるようにしました。
–海と富士の茶の間には、海外の方々も多く訪れているそうですね。
いろんな国の方にご利用いただいていますよ。台湾からは著名な茶師 張家獻さんが日本茶を学びに来日された際に、この海と富士の茶の間を利用されました。
 ▲左が本多茂兵衛さん。右が台湾で著名な茶師の張家獻さん。
▲左が本多茂兵衛さん。右が台湾で著名な茶師の張家獻さん。
南米大陸ご出身の方がいらした際には、海の方向を指さして「あちらの方角にずぅ~っと進むと貴方の国ですよ」とお話しすると感激してくれます(笑)

「茶園」という新しいフィールドの可能性
「海と富士の茶の間」を取り囲み、その空間を演出する茶園。ここは富士山まる茂茶園の生産収穫の現場でもあり、さまざまな品種のお茶が栽培されています。

–ここでは、どのような品種のお茶が栽培されているのですか?
たくさんの品種のお茶が植えてありますよ。この茶の間の周りに植えられているのが、夏に紅茶を作ると美味しい「さやまかおり」。

奥にあるのが日本一のポピュラーな品種「やぶきた」。

1段高いところが「めいりょく」。釜炒り茶や白茶、烏龍茶を作るのに適した品種です。

それに宮崎で開発された品種「さきみどり」。烏龍茶にすると面白い香味が出ます。

このようにさまざまな品種を栽培することで、1年中何かしらのお茶の体験ができるようにしています。寒い時期には、越冬のために糖分を蓄えた硬い葉でほうじ茶が作れますし、事前に予約をいただければ、手揉みや釜炒りも受け付けますよ。

–「海と富士の茶の間」にはさまざまな利用方法があるのですね。
お茶の体験だけでなく意外な形で利用されたりもしますよ。茶道の先生は野点を楽しんでいましたし、音楽家が尺八と琴を奏でている光景は幻想的でした。
夏や晩秋にはバーベキューや鍋をすることもあります。海と富士山を眺めながら焼き芋や燻製で賑わうのは何度やっても飽きない。そして私はそれに合うお茶をペアリングするべく腕を振っています(笑)



なかには「何もしない時間」を過ごしに来る方もいます。特に海外からのゲストは、限られた時間で西に東に慌ただしく移動している方が多い。そんな道中で必ず30分から1時間、何もしない時間を作ります。
異国の安全な場所で誰にも邪魔をされず、リラックスした時間に浸れる機会を「茶園」というフィールドを活用して提供したいですね。
 ▲海と富士の茶の間から眺める夕暮れの富士山
▲海と富士の茶の間から眺める夕暮れの富士山
富士御茶の香味はどこから来るのか–富士山麓の茶師が語るお茶の味が産地で異なる理由–
(海と富士の茶の間で本多さんに呈茶していただきながら、そのお茶作りについてお話を伺いました)
「海と富士の茶の間」にいらした方々には、煎茶、ほうじ茶、紅茶をご用意しています。これは私の作るほうじ茶で、丸火(まるび)といいます。丁寧に選別した茎のみを、3日間じっくりと独自の製法で焙煎しました。スモークされたような香りと甘みがすると好評をいただいています。
–どのお茶も美味しい。しかし、今まで私が飲んできたお茶の味とはどこか違います。

 ▲本多さんの作るお茶は「富士御茶(ふじおんちゃ)」と呼ばれており、その芳醇な香味は国内外で高く評価されています。
▲本多さんの作るお茶は「富士御茶(ふじおんちゃ)」と呼ばれており、その芳醇な香味は国内外で高く評価されています。
–なぜお茶は産地によって味が異なるのでしょうか?
「お茶」とは、ピーマン、茄子、トウモロコシのような「単年性作物」ではありません。定植してから収穫まで長い年月を要する「多年性作物」なのです。桃や葡萄といった果樹と同じように、「樹」に分類されます。

「樹」という作物は、長く育てることで地中に根を下ろし、横に広がります。その範囲は非常に深く、地表から50センチ以上下の地層にまで及びます。そうして伸びた根が地層から吸い上げるミネラルや鉱分が、口に含んだ後の余韻に繋がるのではないかと私は考えています。

分かりやすい例を挙げると、富士川を挟んだ東西でお茶の味は異なります。この「海と富士の茶の間」が位置する富士川の東側の地層は溶岩の岩盤ミネラルを吸い、富士川の西側は赤土のミネラルを吸うため、味に違いが出てきます。茶産地としての味の特徴を形成するのは、こうした部分が影響しているのだと思います。
 ▲手前側が茶の間のある富士川の東側、向こう側が富士川の西側に位置します。
▲手前側が茶の間のある富士川の東側、向こう側が富士川の西側に位置します。
–なるほど、静岡はフォッサマグナなど複数の地層の上に位置していますから、同じ静岡県内でも産地が変われば地層の成り立ちも異なります。理にかなった考えですね。
土壌の表層50センチも、もちろん味を構成する要素のひとつでしょう。1煎目に旨味がのるかどうかは、この表層50センチに蓄えられた肥料の効果に関係します。
肥料の効果はその年の天候にも左右されます。雨が多ければ肥料は流亡(流出)してしまい、逆に雨が全くなければ水分不足で作物に吸収されません。

肥料をどのように施すかは土質によって大きく変わります。ここ富士の土地は、富士山の火山灰から成る「黒ボク土」です。リン酸係数が高く、有機物の分解スピードが少し遅いため、肥料を入れ過ぎると分解されずに吸収されず、逆効果になります。
これがもし掛川の土地であれば、また違った判断がされるのでしょうね。実際に行って調べてみると、静岡県西部の掛川と東部の富士では土質がまるで違います。

つまり、茶園の管理者がどのようなコンディションで表層の土壌を作り、環境の変化に対応しながら施す処置が、最終的に「お茶のキャラクター」を形作っていくのだと思います。
さらに、地層からのミネラル分が掛け合わさることで、ようやく茶の香味が決まるのです。ですから、「このお茶は肥料を沢山入れているから美味しい」といった単純な話にはならないのです。

真実は誰にも分からず、多くは茶の樹に秘められる
–本多さんは、お茶の味がどのようにして作られていくのかを言語化して説明してみせることができるのですね。
お茶作りの過程を言葉で説明するというのは、あくまで私の個人的な方法です。私はただ茶師として、何が美味しくて、何が心地よくて、何が不味いのかを理解し、説明できるようでありたいだけです。
多くの人々は、それぞれの土地で培ってきた経験則に基づいて作業を行っていると思います。それがその土地に合った結果ですから、それを否定するつもりはありません。そもそも、私は「これが正しい、これが間違っている」と言いたいわけではないんです。
エモーショナルな部分で感動をお茶に求めてもらうのも、もちろん良いことだと思いますよ。

お茶は農産加工品なので、さまざまな過程で自然や人の手が加わり、その結果について原因を特定するのは難しいものです。お茶のどの香りがどこから来ているのか、原因が土地なのか栽培法なのか製法なのかを特定することはできません。あくまで私が技術的に再現できるというだけです。
お茶は農産加工品なので、さまざまな過程で自然や人の手が加わり、結果に対しての原因究明が難しい。お茶のどの香りがどこから来ているのか、原因が土地なのか栽培法か製法か特定するまではできません。あくまでも私が技術的に再現できるというだけです。
結局のところ、お茶を語る際の基本的なスタンスは「真実は誰にも分からず、多くは茶の樹に秘められる」で臨むことがオススメです(笑)。
関連記事:五代に渡る茶師の情熱が生む、富士山まる茂茶園の恵み「富士御茶」【静岡県・富士御茶】
関連記事:大地の茶の間で味わう茶産地牧之原のテロワール【静岡県・牧之原市】
おすすめ記事 : 静岡の自然溢れる日本茶カフェおすすめ5選!カップルにピッタリなお茶デートの楽しみ方
~海と富士の茶の間の情報・購入方法・茶園体験の申し込み~
| 住所 | 〒417-0841 静岡県富士市富士岡1765 |
| ホームページ | 「海と富士山の見える茶園」の体験予約はこちら |
| https://www.instagram.com/honda_mohei/ | |
| 電話番号 | 0545-30-8825 |
| 電子マネー・カード決済 | クレジットカード対応済み
QRコード決済非対応 |
| 営業時間 | 問い合わせ |
| 定休日 | 問い合わせ |
| 駐車場 | あり(少数台) |
| アクセス | 最寄り駅、新富士駅より車15分
吉原駅より車15分
国道1号線富士東インターを降りて北上、県道76号線を北上し、 県道22号線との交差点を直進、坂道手前を右折、赤淵川を渡ってすぐを左折して200m |
| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |
| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~24年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズは世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介されています。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |
| 英訳担当 | Calfo Joshua |
| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |
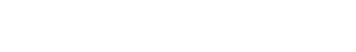
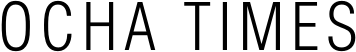
 Go to English page
Go to English page










 をクリックするとスライドが閉じます。
をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。
をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。