茶屋すずわの合組茶が描く美味しい情景【静岡県・静岡市】

静岡県は日本最大のお茶の産地であり、日本中からお茶が集まる流通の中心地です。静岡駅から北西に1.5kmほどの場所に位置する茶町には、静岡茶市場があります。新茶の時期には、多くの茶問屋が取引を行い、活気に満ちた賑わいを見せます。今回取材したのは、静岡茶市場から徒歩10分ほどの場所にある鈴和商店。創業170年以上の歴史と伝統に裏付けされた高度なお茶づくりの技術を持つ老舗茶問屋です。工場に併設した店舗や、SNSを活用してお茶の魅力を積極的に発信しており、多くの人々にお茶を届ける活動にも熱心です。
この記事では、茶屋すずわの目指すお茶屋の在り方や、日常の暮らしを豊かにするお茶の楽しみ方を、鈴和商店の6代目である渥美慶祐さんのインタビューを交えながらお伝えしていきます。
目次
茶屋すずわとは
「茶屋すずわ」は2019年に、茶問屋鈴和商店の茶工場に併設されたお茶屋です。運営元は創業が嘉永元年(1848年)の老舗茶問屋鈴和商店。江戸時代より170年、お茶を作り続けており、現在の代表は6代目の渥美慶祐さんです。

 ▲茶屋すずわを営む鈴和商店は、そのお茶づくりの高度な技術により数々の賞を受賞しています。
▲茶屋すずわを営む鈴和商店は、そのお茶づくりの高度な技術により数々の賞を受賞しています。
長らく茶問屋鈴和商店は主に卸売に従事し、小売には取り組んでいませんでした。しかしその間、多くのお客様が直接鈴和商店にお茶を求めて訪れることがありました。このため、かつて駐車場として使用していた場所にお茶屋を設け、お客様を歓迎する場所を整えることにしました。こうして「茶屋すずわ」が誕生しました。

店内はケルト的な雰囲気で、一見するとお茶屋とは思えない趣。茶屋すずわオリジナルブレンドのお茶や渥美さんが厳選した作家の茶器が陳列されています。
茶屋すずわに置かれている茶器は、全て渥美さんが自ら使用して気に入ったものばかりです。気に入った作家には、特注のオーダーを出すこともあるそうです。現在、10人以上の作家の茶器が展示されています。

店内の一角に、趣のある茶器が展示された棚があります。こちらは渥美さんのこだわりの私物が並んでいます。
渥美さんはクラフトのイベントや個展に行くたびに、良さそうな茶器を見つけるとついつい購入してしまうそうで、その中からいくつかをインテリアとして店内で展示しています。
 ▲渥美さんの私物が飾られている棚(売り物ではありません)
▲渥美さんの私物が飾られている棚(売り物ではありません)
茶屋すずわのお茶の紹介
茶屋すずわでは、合組茶(合組とは、茶師の伝統技術で、異なる産地の茶葉を配合して複雑で立体感のある香味のお茶を作り出すもの。ブレンドとも表記されます)から、単一品種単一産地のシングルオリジン茶など、幅広い種類のお茶を購入できます。

オリジナリティ溢れるイラストパッケージのお茶は、お茶の素晴らしさを広めるためにつくられた茶屋すずわオリジナルブランドのお茶です。特に、「お茶の時間の贈り物」シリーズは、渥美さんの願いで「お茶の情景的な部分も楽しんでほしい」という想いが込められています。
コンセプトは人々の暮らしに寄り添うお茶。こだわりの合組茶は日々の暮らしを彩る素敵な一杯になるでしょう。ここでは、茶屋すずわのお茶を少しだけ紹介します。

【いつものとき】めざめのお茶
最高の一日の始まりにぴったりなお茶です。「大切な一日を爽やかな気分で始めてほしい」というコンセプトに基づき、静岡市の安倍川流域の煎茶と香り高くほのかな渋味のある天竜産の煎茶、そして芽茶が合組されています。
香りとバランスの良い味わいは、一日のスタートを爽快に彩ります。茶葉タイプとティーバッグタイプの2種類から選べます。

【いつものとき】おやつのお茶
おやつの時間を楽しく彩る一杯です。「お気に入りのおやつと共にリフレッシュする時間を過ごしてほしい」というコンセプトのもと、牧之原の深蒸し茶が使用されています。濃緑色の美しい色合いは、淹れた瞬間に目でも癒しを感じます。
渋みが少なく、コクがあり、柔らかい飲み口の味わいは、甘味のあるおやつと相性抜群です。茶葉タイプとティーバッグタイプの2種類から選べます。

【いつものとき】おやすみのお茶
おやすみのお茶は、一日の終わりのリラックスタイムに最適です。牧之原・天竜の茎茶を使用したこの焙じ茶は、「がんばった一日の終わりに、くつろぎの時間を過ごしてほしい」というコンセプトのもとに合組されました。リラックス効果のある香り成分を含む焙じ茶は、寝る前におすすめ。
まろやかで優しい香りが特徴です。茶葉タイプとティーバッグタイプの2種類から選べます。

月花蜜~夕顔の茶~
料理の香りと旨味に見合うため、通常の緑茶には含まれない強い花香を持つ在来実生種の茶を使用されています。この茶葉は釡炒り後に発酵させ、白葉茶(99.99%日光を遮光し旨味成分が通常の煎茶の何倍も含まれる茶葉)を独自の比率で合わせているそうです。

 ▲月花蜜~夕顔の茶~は料理家夕顔さんがディレクションし、イラストレーター山口洋佑氏がパッケージデザインを手がけました。
▲月花蜜~夕顔の茶~は料理家夕顔さんがディレクションし、イラストレーター山口洋佑氏がパッケージデザインを手がけました。
香りはマスカットのような華やかさで、花の蜜を思わせる甘味と絶妙なバランスを保っています。料理家「夕顔」と茶屋すずわが共同で試行錯誤して生み出した、奥深い複雑さと親しみやすさを兼ね備えた特別なお茶です。

インタビュー:変わりゆく時代において茶屋すずわが見出す新しいお茶屋の在り方

鈴和商店6代目取締役の渥美慶祐さんにお話を伺いました。
茶問屋の合組技術こそ静岡の茶町を支える誇り
–「茶屋すずわ」のお茶づくりについて教えていただけますか?
「茶屋すずわ」では、合組にこだわったお茶づくりを行っています。最近ではシングルオリジン茶(単一産地単一品種の茶。個性的な香りと味わいが特徴)が人気ですが、茶問屋の合組により生まれる奥深い香りや味わいはシングルオリジンにはないものだと考えています。

 ▲小売り店に隣接した場所には、お茶の拝見場が設けられています。ここでは何十種類ものお茶を日夜テイスティングしながら、品質を見極め、お茶づくりを行っています。
▲小売り店に隣接した場所には、お茶の拝見場が設けられています。ここでは何十種類ものお茶を日夜テイスティングしながら、品質を見極め、お茶づくりを行っています。
–合組とは簡単に言うと異なる産地の茶葉をブレンドすることだと聞いています。具体的にはどのような技術なのですか?
例えば、日照時間の短い山間部で生産される浅蒸し茶は、独特の香りと甘味が特徴的ですが、水色は薄いものです。一方、日照時間の長い平地で生産される深蒸し茶はコクがあり、色鮮やかな緑色の水色が特徴ですが、香りは弱い傾向にあります。簡単に言うと合組とは、そうした長所を組み合わせる技術なのです。
お茶の葉を量や質の面で安定したお茶に仕上げる上で、非常に重要な加工工程です。

茶問屋の確かな技術に基づいて合組されたお茶は、単にお茶の良いところを組み合わせただけのものではありません。産地ごとにどのようなお茶が作られるのかを見極め、焙煎や仕上げを通じてそのポテンシャルを最大限に引き出す工程は、まさに「お茶の味と香りの再構築」と言えるでしょう。
そして、私の知る限り、静岡の茶問屋が持つ「お茶を見る技術」「味と香りを判断するテイスティングの技術」は、本当に優れていると思います。それが静岡をお茶の町と呼ばせる理由の一つでもあるのです。

–確かに、お茶は農作物である以上、毎年同じものになることはありませんね。その年のお茶の特徴を見極める技術が合組茶の出来栄えを左右するというのは納得です。
私たちはこの先も合組の技術を磨き、最高の一杯を追求していきたいと考えています。この道は一生かけても終わることはありません。

–「合組技術をもって最高のお茶を作る」ことは、茶問屋としての目標でもあるのですね。
ただ、誤解してほしくないのは、どのお茶が一番だとか、良い悪いとかを主張したいわけではないんです。みんなの味覚はそれぞれ違いますし、そこは競うものではありませんから。それはお客さん自身が判断することだと思います。
でも、私たちが純粋に作り上げたお茶が「美味しいね」と言ってもらえると、作り手としては最高なんです(笑)

変動する時代の中での課題「茶問屋に求められる新たな役割とは」
かつては日本茶といえば、茶問屋が作る伝統的な合組茶が主流でした。しかし、最近ではお茶のブレンドに対するイメージがあまり良くないと感じています。シングルオリジン茶の人気が高まり、ネットショップなどを通じたお茶の流通も拡大しています。
このような状況の中で、茶問屋として私たちが果たすべき役割は何なのか、常に自問自答しています。

本音を言えば、茶問屋としては単一産地で仕入れ、単一産地単一品種のお茶を販売する方が遥かに楽なのです。しかし、伝統ある合組技術こそが茶問屋の真価です。それは揺らぎません。
–一昔前に比べてお茶の流通は大きく進化しましたが、ただお茶が流通するだけと、茶問屋の「厳しい目利き」を通過したお茶が流通するのとでは、大きな違いがあります。しかし、その部分を消費者に伝えることは難しいかもしれませんね。

静岡はお茶の生産地だけでなく、全国からお茶が集まる集積地でもあります。そのため、お茶に触れる機会が多く、自然とお茶の品質を見極める目が養われます。この感覚こそが私たちの技術そのものなのです。
この部分をもっとうまく表現できないだろうか、と考えています。その先に、消費者が見たときに私たち茶問屋の新しい価値や役割があるのではないか、と思っています。
–お茶を表現する方法や伝え方に、「お茶を見る技術」「味と香りを判断するテイスティングの技術」を活かせないかと考えているんですか。
“静岡茶”と一括りにされることが多いですが、静岡県内には様々な茶産地があり、お茶が育つ環境も異なります。これらの違いを伝えることは、私たち茶問屋が担うべき役割だと感じています。

日常を豊かにするお茶の新たな可能性を求めて
今は本当にお茶を飲む人が少なくなってきています。しかし、皆がお茶が嫌いというわけではありません。問題なのは、お茶の良さが伝わっていないことだと思います。
そうした魅力を伝えるために、お茶の香りや味わいはもちろんですが、「お茶ならではの豊かなひととき」にもっと焦点を当てていけないだろうかと考えています。


–「お茶ならではの豊かなひととき」ですか。
私はお茶の味や香りではなく、飲んだときに情景が浮かぶお茶をつくりたいと考えています。お茶に産地名や品種名をつけるのも良いと思いますが、そもそもお茶にそれほど興味を持たない人に、品種名や産地名を伝えて魅力が伝わるのか疑問です。
そのため、茶屋すずわではネーミングやデザインに工夫を施しました。パッケージには小鳥のロゴが入っています。このロゴは「新しい未来への飛翔を」という意味を持ち、お祝い事でもお茶を使用してほしいという願いや、「飛び立つ鳥が羽を休める止まり木のようなお茶屋でありたい」という願いが込められています。

そうしたら、セレクトショップや雑貨屋さんにも取り扱ってもらえるようになりました。これにより、これまでお茶に触れる機会がなかった人々にもアプローチできるようになっていることを感じています。

–これまでお茶がなかった場所にお茶を取り入れ、その成果を感じているのですね。SNSでの発信も、そうした発想のもとで行っているのですか?
はい。SNSを活用することで、お茶の魅力を手軽に他の業界にも伝えることができるので、積極的に利用しています。実は私もお茶の写真を撮るのが好きで、その魅力を伝える手段としています。
–私も見ましたが、花火のように撮影されたお茶の写真は本当に美しく、見とれてしまいました。
 ▲茶屋すずわのSNSに載せたお茶の写真
▲茶屋すずわのSNSに載せたお茶の写真
お茶といえば緑茶というイメージがありますが、実は水色一つとっても沢山の色のお茶があります。それを伝えるために、視覚的にたくさんの色合いを楽しめる写真を撮ることにしました。
–着色料を加えないで、これだけ多くの水色がある飲み物はお茶しかないかもしれませんね。
私たちは緑茶だけでなく、紅茶や発酵茶も作ります。実はお茶は多様性に富んだ飲み物なのに、それがあまり知られていないんです。実際、「日本で紅茶なんて作っているの?」「日本でウーロン茶って作れるの?」と驚かれることが少なくないのです。

お茶の香りと味わいが紡ぐ美味しい情景が届けられたら
–「お茶の多様性や情景的な楽しみ方を伝えていくことが大切」という考えなのですね。
お茶の楽しみ方は自由で良いと思いますよ。その辺の楽しみ方を押し付けるつもりはないですし、そこは決めつけるのが一番駄目だと思います。

でも、お茶は誰と飲むかとか、どんな急須を使うかとか、こんな空気感でとか、そういった外的な要因も味に関係してくるのは確かだと思います。あまり好きでもない人と、かしこまって飲むお茶よりも縁側でおばあちゃんが淹れてくれたお茶の方が美味しい。
カップラーメンだって、富士山の頂上で食べるカップラーメンは凄く美味しいでしょう。そんな情景的な部分も伝えていけたら、もっとお茶が楽しんでもらえるのではないかなと思います。

関連記事 : しずチカ茶店一茶は静岡市のお茶屋の熱意が託されたお茶屋【静岡県・静岡市】
おすすめ記事 : 茶町KINZABURO(キンザブロウ)のデザインする安らげるお茶の空間【静岡県・静岡市】
~茶屋すずわの情報・購入方法~
| 住所 | 〒420-0011 静岡県静岡市葵区安西3丁目68 |
| ホームページ | https://www.chaya-suzuwa.jp/ |
| SNS | |
| 電話番号 | (054)271-1238 |
| 電子マネー・カード決済 | 対応済み |
| 営業時間 | 平日10時〜16時半 第2.4土曜 11時〜18時 |
| 定休日 | 木、土曜、日曜日、祝日 |
| 駐車場 | あり |
| アクセス | JR静岡駅から車で約15分 |
| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |
| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~24年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズが世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介される。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |
| 英訳担当 | Calfo Joshua |
| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |
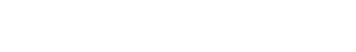
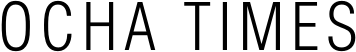
 Go to English page
Go to English page










 をクリックするとスライドが閉じます。
をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。
をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。