お茶とともに。地域とともに。飲み手の笑顔のために──鈴木茶苑が守る「生活に寄り添う味わい」【静岡県・川根茶】

南アルプスの山間地、静岡県川根本町徳山。人口約1,000人のこの集落で、多品種のお茶づくりに取り組むのが「鈴木茶苑」です。自園・自製・自販で煎茶、紅茶、釜炒り茶などを生産・販売しながら、SNS発信やイベント出店などを通じて、お茶の魅力を広く届けています。ペットボトルやコーヒーなど、さまざまな飲み物が手軽に手に入る今でも「お茶が人々の生活に寄り添う存在であり続けてほしい」。そんな想いを胸に、お茶作りを続ける鈴木茶苑にお話を伺いました。
この記事では、鈴木茶苑がなぜ個性豊かなお茶を作るようになったのか、お茶を手に取る人の笑顔を想像しながら作る大切さなど、鈴木健二さんのインタビューを交えてお届けします。
目次
鈴木茶苑とは
鈴木茶苑(すずきちゃえん)は、静岡県川根本町徳山にある自園・自製・自販の茶農家です。煎茶をはじめ、紅茶や釜炒り茶など、さまざまな品種の特性を活かしたお茶づくりを行っています。
現在の代表は、2代目・鈴木健二さん。先代の故・鈴木勝彦さんは、静岡県中山間100銘茶協議会の初代会長を務めた人物でもあります(現会長は、富士山まる茂茶園の五代目・本多茂兵衛さん)。

予約制茶工場カフェ「ぽち」について
鈴木茶苑では、事前予約制の茶工場カフェ「ぽち」を運営しています。ご予約は Instagram または X(旧Twitter) のDMにて受け付けています。なお、自宅では小売りを行っておらず、事前連絡のないご訪問には対応できません。あらかじめご了承ください。


鈴木茶苑のお茶の紹介
静岡県川根本町徳山にある鈴木茶苑の茶畑では、在来種をはじめ、有名な「やぶきた」や希少品種の「ふじみどり」「くらさわ」など、多様な品種茶を栽培しています。品種ごとの個性を生かして製造された煎茶、釜炒り茶、紅茶などを、主に通販で販売しています。
お茶の名前はすべて自分たちで考案しており、発酵茶に使われている「青獅子(あおじし)」や「山翡翠(やませみ)」などの名前は、この地域に生息する動物にちなんでいます。名付け親の多くは、妻のかほりさん。お茶の味わいだけでなく、名前の由来を調べてみるのも、自園・自製・自販でつくる鈴木茶苑のお茶ならではの楽しみ方です。
なお、お茶のラインナップは時期によって変わることがあります。最新情報は鈴木茶苑のホームページをご覧ください。

【編集部メモ】このあと、鈴木茶苑の取り組みや想いをインタビューで詳しくご紹介します。あわせて、作り手の現場を取材した茶農家の取材記事一覧もぜひご覧ください。
インタビュー:地域とともに、お茶とともに。飲み手の笑顔のために。鈴木茶苑が描く、やさしいお茶のかたち

鈴木茶苑の鈴木健二さんにお話を伺いました。
「青獅子」と「山翡翠」が語るもの──鈴木茶苑のパッケージに宿る、お茶の個性と地域の魅力
–今の時代にお茶の魅力をどう広めていくか、そのビジョンをお聞かせいただけますか?
コンビニやカフェで多種多様な飲み物が手軽に手に入る今の時代。その中で、急須で淹れるリーフ茶は「手間がかかる」と感じられることも少なくありません。そうした背景を踏まえ、鈴木茶苑では早くからお茶の魅力を広く伝える取り組みを始めました。単にお茶を販売するのではなく、伝え方にも工夫を凝らしています。
たとえば、お茶の種類が一目でわかるように、パッケージのデザインをお茶ごとに変えています。釜炒り茶はクラフト紙、紅茶は黒、煎茶は白と、それぞれのお茶の個性に合わせたデザインに仕上げています。
 ▲被覆茶のイメージから「青獅子」という名前を採用。ロゴマークのデザインも鈴木茶苑が手がけています。
▲被覆茶のイメージから「青獅子」という名前を採用。ロゴマークのデザインも鈴木茶苑が手がけています。
–鈴木茶苑では、発酵茶という少し珍しいお茶も手がけていますね。そこにはどのような想いがあるのでしょうか?
もともと父が発酵茶に可能性を感じていたこともあり、私たちも比較的早い段階から発酵茶の製造と情報発信に取り組んできました。そうした取り組みの積み重ねが少しずつ実を結び、最近ではSNSなどで取り上げていただく機会も増えています。とてもありがたいことだと感じています。
 ▲イベントで呈茶を行う鈴木茶苑 右:故・鈴木勝彦さん 左:鈴木健二さん
▲イベントで呈茶を行う鈴木茶苑 右:故・鈴木勝彦さん 左:鈴木健二さん
–静岡型発酵茶「青獅子(あおじし)」や釜炒り発酵茶「山翡翠(やませみ)」といった名称も印象的ですね。
ありがとうございます。こうした名前を付けているのは、川根本町・徳山という地域の魅力も一緒に伝えたい、という想いからです。
この地域は、新茶の季節だけでなく、一年を通してさまざまな美しさが楽しめます。夏は蛍が舞い、秋には山の紅葉が鮮やかに色づきます。冬はバードウォッチングを楽しむ人も多く、珍しい野鳥に出会えることも。春には枝垂れ桜の並木道が、訪れる人の心を癒してくれます。

また、徳山の盆踊りや神楽といった伝統芸能も大切に受け継がれていますし、すぐそばを走る大井川鉄道では、今も蒸気機関車が現役で走っています。こうした地域の魅力も、お茶と一緒に届けられたら嬉しいですね。


「水色」よりも「味と香り」。「茶葉の形」より「飲み手の笑顔」。鈴木茶苑が守るお茶の原点
鈴木茶苑では、「爽快感のある香りと、穏やかで自然な甘み」こそが本来のお茶の魅力だと考えています。ところが近年、茶業界では、抽出液の色である「水色」、抽出前の茶葉の形状、そして成分分析による「旨味成分」の数値に重きを置く傾向が強まっています。
本当にそれは、お茶を飲む方々の求めるものなのでしょうか。お茶を手に取る人の笑顔を想像しながら作られてきたのでしょうか。「お茶が売れなくなった」とよく耳にしますが、私には「飲み手」の視点を置き去りにした結果ではないかと感じられてなりません。

–お茶が売れなくなってきている原因は、そうした業界の姿勢にあるとお考えですか?
いくつかの要因が重なっているとは思います。今の時代、昔と比べて選べる飲み物の種類は格段に増えましたし、どれも手軽に、しかも安価で手に入ります。そういった流れの中で、急須で淹れるお茶が敬遠されるのも、ある意味では自然なことかもしれません。
ただ、それに加えて「水色」や「茶葉の形状」に過剰にこだわりすぎるあまり、「香り」や「味」といったお茶の本質的な魅力が後回しにされているように感じます。そうした傾向が、お茶の本来の価値を伝えきれず、お茶離れに繋がっているのではないかと感じています。

ペットボトル茶はお茶に触れる第一歩。変わりゆく時代をつなぐ、お茶文化の入口
–リーフ茶の売り上げが減少している要因として、ペットボトル茶の存在を挙げる声もありますが、その点についてはどうお考えですか?
私は、ペットボトル茶がリーフ茶の「敵」だとは思っていません。むしろ、励みになる存在だと捉えています。大手の飲料メーカーが次々とペットボトル茶を展開しているのは、それだけお茶が今も多くの人に求められているという証拠だと思います。
急須を持たない家庭が増えている現在、もしペットボトル茶がなかったら、お茶そのものに触れる機会すらなかった人も少なくないでしょう。そう考えると、ペットボトル茶は「お茶の入り口」のような存在であり、お茶文化を守る上でも重要な役割を担っていると感じます。

今の時代は、あらゆる商品や情報があふれています。そんな中で、変わらずお茶が選ばれ続けているという事実に、私は大きな励ましを感じています。「お茶を手に取ってくださる方が、まだこんなにもいるんだ」と。
ペットボトル茶を飲んでいる方々のうち、ほんの一割でも急須で淹れるお茶に興味を持っていただけたら。そんな思いがあります。そして、そのときに私たちがどれだけ魅力あるお茶を提供できるかが、お茶の文化を広げていく上でのカギになると思っています。
そして、そこにこそ、自分が茶業に携わる意味と責任があると感じています。

大量生産大量消費の時代に、「誰かの笑顔に応えるお茶」を。鈴木茶苑が歩む、やさしき挑戦
–鈴木茶苑のホームページには、お茶の情報や淹れ方などがとても詳しく紹介されていますね。
基本的に、お茶は皆さんが自由なスタイルで楽しんでいただけたらと思っています。ホームページでご紹介している淹れ方も、あくまで「ひとつの参考」として見ていただければ嬉しいです。
お茶を作る人それぞれに個性がありますし、農家ごとの特色もさまざまです。そういった違いを活かしながら、多様なお茶の楽しみ方や届け方を提案していきたいですね。

世の中の多くのものが、大量生産・大量消費の流れの中にあります。お茶もその影響を受けていることは否定できません。そして近年では、嗜好品としての側面がより強くなり、少し硬直化してしまっているようにも感じています。
けれど私は、それを決して悲観的には捉えていません。むしろ、これからの時代に必要なのは、「誰かの笑顔に応えるお茶」をつくり、届けていくことだと思っています。そして、その未来には、希望しかありません。

~鈴木茶苑の情報・購入方法~
| 住所 |
〒428-0301 静岡県榛原郡川根本町徳山982 ※事前予約なしの訪問はお断りしています |
| ホームページ | https://kawanecha.thebase.in/ |
| 電話番号 | 0547-57-2612 |
| 電子マネー・カード決済 | ネットショップのみあり。
現地での小売りはしていません。 |
| 営業時間 | 問い合わせ |
| 定休日 | 問い合わせ |
| 駐車場 | あり(少数台) |
| アクセス | 鉄道の場合 東海道線「金谷駅」乗り換え大井川鐵道「駿河徳山駅」(所要時間約1時間)で下車し徒歩20分自動車の場合 東名高速:相良牧之原I.Cから約1時間20分 国道1号:島田市から約1時間 |
| この記事を書いた人 | Norikazu Iwamoto |
| 経歴 | 「静岡茶の情報を世界に届ける」を目的としたお茶メディアOCHATIMES(お茶タイムズ)を運営。2021~25年に静岡県山間100銘茶審査員を務める。静岡県副県知事と面会。お茶タイムズは世界お茶祭りHP、お茶のまち静岡市HP、静岡県立大学茶学総合研究センターHP、農林水産省HPで紹介されています。地元ラジオやメディアに出演経験あり。 |
| 英訳担当 | Calfo Joshua |
| 経歴 | イギリス生まれ育ち、2016年から日本へ移住。静岡県にてアーボリカルチャーを勉強しながら林業や造園を務めています。カルフォフォレストリーを運営。日本の自然を楽しみながら仕事することが毎日の恵み。自然に重点を置く日本の文化に印象を受けて大事にしたいと思ってます。 |
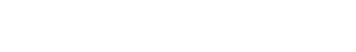
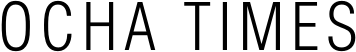
 Go to English page
Go to English page










 をクリックするとスライドが閉じます。
をクリックするとスライドが閉じます。 をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。
をクリックするとグーグルマップで見れて現在の位置から茶屋までの距離、道順が分かります。